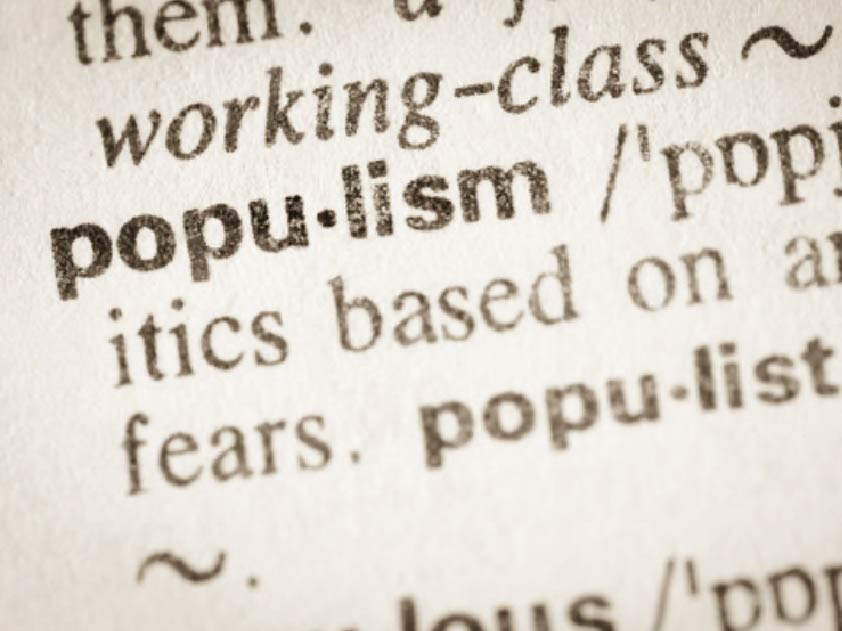立憲民主党の枝野氏が、12日の講演で「減税だ、給付だ、というのは参院選目当てとしか言いようがない。減税ポピュリズムに走りたいなら別の党をつくれ…」と発言したことが党内で問題になっているようです。
枝野氏とは反対に、同党の選挙対策本部長代行の小沢一郎氏などは「消費減税を党の政策として掲げるべきだ」との認識を示しています。
さて、先日の当該ブログでも少し触れましたが、枝野氏の言う「減税ポピュリズム」とは、おそらくは「減税は、それを求める愚かな大衆に迎合した政策だ」という意味合いの批判かと思われます。
つまり枝野氏は「ポピュリズム」を「大衆迎合」という意味で使っているものと拝察します。
枝野氏のみならず、日本のメディアも同様の解釈をしていますが、ポピュリズムを「大衆迎合」と訳すのは、明らかな誤訳だと思います。
その理由は以下のとおりです。
もともと「ポピュリズム」というのは、1880年代に米国の中西部の農民運動からはじまった言葉です。
当時はちょうど第二次産業革命の時代です。
すなわち、鉄鋼、鉄道、石油などの産業が大いに華やいだ時代で、これらの産業は規模の経済が働いた産業であったため、勝者総取り経済の絶頂でした。
よって、鉄鋼王や鉄道王や石油王と呼ばれる財閥が形成されるとともに、いわゆるグローバリズム経済の恩恵を受けた東海岸の資本家たちが儲けに儲けたことで、米国社会には強烈な格差が生じていきました。
そうした社会問題に対し、当時の共和党も民主党も何ら解決策をもたず、ただただ金持ちの言うことしか聞かず、苦境に立たされた国民たちの深刻な訴えに対して全く聞く耳をもっていませんでした。
まるで、財務省の言うことは聞いても国民の言うことは聞かない、今の日本の政治と同じです。
前述した中西部の農民たちは、苦しんだ国民の一部でした。
デフレ経済や技術革新の影響も相まって穀物価格は下がり続け、彼らの収入はひたすら減り続けました。
なかには東海岸の資本家たちにカネを貸し付けられ、カネを返せぬ農民たちは土地をも奪われていったのです。
まさに自由放任経済の歪みです。
それでも共和党や民主党という既存政党は何ら対策を打たない。
これに怒った中西部の農民たちは、ついに既存政党に抵抗する同盟運動を起こしたのです。
その運動に都市部の労働者たちも加わり同盟運動は大きなものとなり、やがて第三の政党をつくるにまでに至りました。
その政党が、「人民党」(Peoples Party)です。
この運動こそが、まさにピープル(People)イズム(ism)、即ち「ポピュリズム」です。
結果的に、彼らの主張は民主党に奪われてしまい、残念ながら人民党は解体することになるのですが、このポピュリズム運動は政治の世界に徐々に浸透していき、これが1930年代のニューディール政策による農業保護政策に大きく結びついたのです。
この意味において、中西部の農民たちからはじまった「ポピュリズム」運動は実に意味のある真っ当な運動だったのです。
はたして枝野氏は、こうした歴史を知った上で「ポピュリズム」という言葉を使っているのでしょうか。