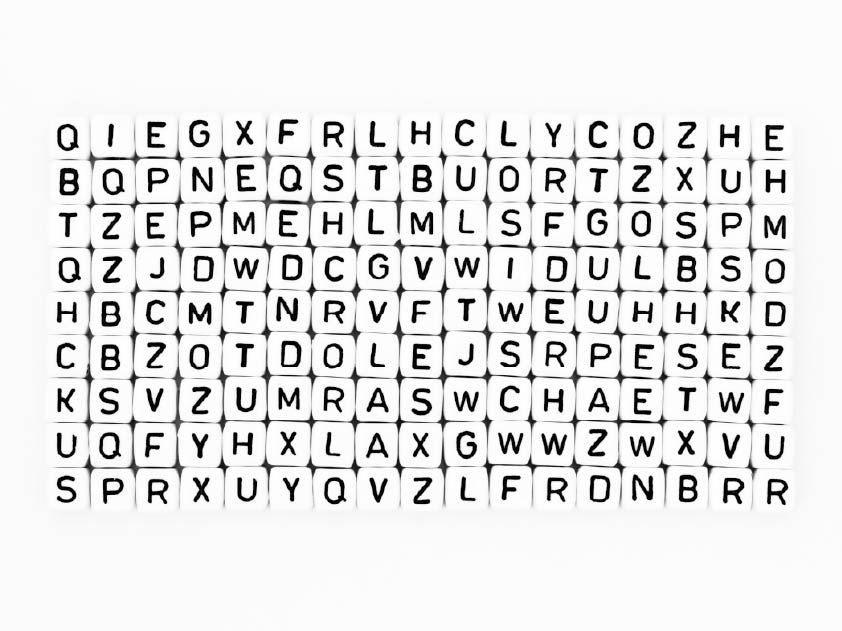きのう(4月18日)のブログでドーリットルB25爆撃機隊による川崎空襲について取り上げましたところ、各方面の皆様から「初めて知りました」などのご反響を頂きました。
川崎は終戦間際にも大空襲を受けているのですが、対米戦のある種の転換点となったという意味においては、昭和17年4月18日の空襲もまた忘れてはならないものだったと思います。
また、奇しくもその翌年(昭和18年)の4月18日には、山本五十六(連合艦隊司令長官)がソロモン群島上空において待ち受けていた米軍機に撃ち落とされ機上戦死しています。
なぜ米軍機が待ち受けていたのか?
むろん、日本軍の暗号が既に米国側に筒抜けだったからです。
司令長官の行動予定が敵に筒抜けでは、そもそも戦争に勝てるわけがない。
戦後、「戦争末期には日本軍の暗号は解読されていた…」と言われてきましたが、米国側が日本軍の暗号を解読したのは、果たしていつだったのでしょうか。
戦争末期か、戦争中盤か、戦争序盤か。
いずれも違います。
米国側が日本(帝国陸軍、帝国海軍、外交暗号)の暗号解読に成功したのは、驚くなかれ、真珠湾攻撃の約1年3ヶ月前の昭和15年9月30日のことです。
その当時は未だ、米国が日本の暗号を解読するのに概ね30分ぐらいの時間を要していましたが、真珠湾攻撃の直前になると3分ぐらいで解読するようになりました。
米国は3分で解読しているのに、ワシントンの日本大使館が(自国の暗号を)解読するのに30〜40分を要していたといいます。
要するに真珠湾攻撃も米国が事前に把握していたのは当然であり、というより戦争がはじまる前から、すなわち日本政府が開戦に踏み切るかどうかを議論していることまで全て米国は知っていたわけです。
日本政府内では誰と誰が怒鳴り合いの喧嘩をしている、ということまで米国は知っていたのです。
もう、どうしようもないですね。
そのうえで米国は日本への石油供給を止めて追い込み、最初の一発を日本から打たせることに成功しました。
12月7日(米国時間)、真珠湾には最新鋭の空母部隊はおらず、古い戦艦しか停泊していなかったのも、事前に日本軍による攻撃を把握していたからです。
それを、おめでたい日本海軍は「多くの戦艦を撃沈した大勝利」と喧伝しました。
どんなに勇敢な兵隊がたくさんいようが、どんなに優れた武器を保有していようが、どんなに優れた作戦を立てようが、全ての暗号が解読され、内部情報が筒抜けの状態では勝てるはずがない。
あの戦争は、負けるべくして負けたのです。
私たちは、そこから何を学ぶかです。